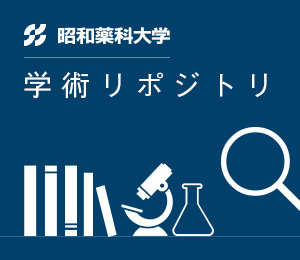薬剤学研究室
創薬?医療の最適化を目指した薬物吸収研究の最前線

ご挨拶
利便性や安全面で優れた経口薬(飲み薬)は、患者QOL視点で最も望まれる投与剤形です。しかし、経口薬は投与条件や消化管内生理環境の影響を受け易いため、企業における開発化合物の経口化や臨床における経口薬の適正使用を実現する上で、その吸収性や毒性を適切に予測することは極めて重要となります。当研究室では、多彩な消化管生理環境?機能に着目し、経口投与後の製剤?主薬の消化管内挙動および吸収制御メカニズムを解明することで、薬物の吸収性、相互作用および消化器毒性を定量的に予測できる方法論の確立を目指しています。また、薬物を目的の場所へ、必要な時間、必要な量を送達させるシステム(Drug Delivery System: DDS)の開発にも取り組んでいます。
研究テーマ
- 薬物-飲食物間相互作用の新規メカニズムの解明
- 消化管内水分挙動の定量的/機構論的解析
- 消化管内生理環境?機能を組み込んだ生理学的薬物吸収動態モデルの開発
- 薬物の吸収部位特性解析に基づく特殊製剤設計の最適化
- 量子ドット/組織透明化技術を活用した薬物吸収動態イメージング解析
- オルガノイド技術を活用した薬物の小児吸収動態/相互作用解析
- 腸内細菌叢/セロトニン動態解析に基づく薬物性消化器毒性予測法の確立
- バイオ医薬の経口DDSおよびその吸収動態解析技術の開発
- ウイルスの機能タンパク質を用いた新規DDSの開発
- 腫瘍微小環境を標的とした新規がんターゲティング療法の開発
研究概要
「薬物吸収」予測のための3つのポイント
ポイント① 細胞膜透過
薬物吸収の理解に重要な第1のポイントとして、消化管上皮細胞を介した「膜透過と代謝」が挙げられます。薬物の膜透過過程には、濃度勾配に従う受動拡散、細胞内外への輸送を担うトランスポーター、さらには細胞内での代謝?分解を担う代謝酵素などが関与します。これらの寄与を分子レベルで解き明かしていきます。
ポイント② 消化管部位差
薬物吸収の理解に重要な第2のポイントとして、「吸収部位差」が挙げられます。全長が長い腸管は、上述したトランスポーター?代謝酵素をはじめ、pH、粘液/水分、絨毛構造、腸内細菌などの特徴が部位毎に大きく異なっています。これら消化管の環境?機能?構造を、最先端の生体イメージング手法などを用いて解明していきます。
ポイント③ 原薬と製剤
薬物吸収の理解に重要な第3のポイントとして、「原薬と製剤」の違いが挙げられます。経口剤は原薬と添加剤を混ぜ合わせて加工された投与製剤であり、例えば、SR錠やOD錠などへの特殊製剤化は、原薬の吸収動態に強く影響します。そこで、製剤の崩壊や原薬の溶解などの物理化学的特性が薬物吸収に及ぼす影響を定量的に解析していきます。
教員紹介
小泉 直也 准教授 / 学位:博士(薬学)
- 研究分野:新たな遺伝子治療戦略への基盤研究
- 担当科目:製剤学(3年次)
薬物送達システム(4年次)
医薬品開発と生産(4年次)
製剤学実習(4年次)
勉強も研究も知的好奇心を刺激してくれるというところは共通点です。ぜひ恥ずかしがらずに好奇心を全開にして取り組んでください。そうすれば苦手な科目も楽しくなってきます。
研究活動も一人一人が楽しむということを最優先で指導しています。もちろん自分が一番楽しんでいます!
野村 鉄也 講師 / 学位:博士(薬学)
- 研究分野:がん微小環境を標的とした新しいがん治療法の開発
- 担当科目:製剤学(3年次)
薬物送達法(4年次)
製剤学実習(4年次)
医薬品開発と生産(4年次)
もっと詳しく