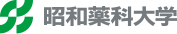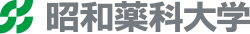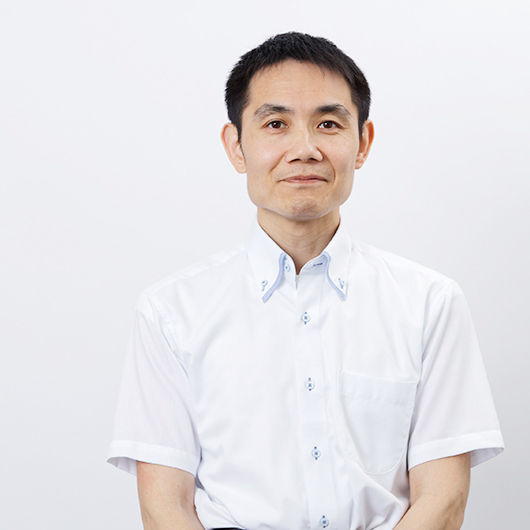薬学について
-
Q.薬学の面白さを、
どんなところに感じていますか?薬学については、面白さよりも難しさを感じることの方が多いというのが率直な感想です。しかし、その難しい問題を解決していく過程こそが、薬学の面白さに繋がっていると感じています。私は決して優秀な学生ではなく、薬がどのように体内で作用するのか、なぜ薬効に違いが生まれるのかなど、薬学のありとあらゆることを理解するのに非常に苦労しました(笑)。難しい内容を理解できた時こそが、薬学の面白さを感じる瞬間ではないでしょうか。
私自身は卒業後に6年間病院薬剤師として勤務しましたが、医師?看護師?コメディカル等の多職種で、患者さん一人ひとりに対して最適な薬物療法を検討していくというのは本当に難しく、大変な仕事だと感じています。薬学的知見から見ると、薬と薬の相互作用、飲み合わせ、さらには患者さんの体調や生活環境など、常に細かい配慮が求められます。これらの難しい問題に直面するたび、その解決策を見出していく過程で薬学の本当の面白さを感じているのかもしれません。
-
Q.昭和薬科大学の魅力は?
私自身も本学の卒業生ですが、学生時代から現在に至るまで昭和薬科大学の魅力として感じていることは「アットホームな雰囲気である」ということです。部活動を通じたOB?OGとの繋がりも深く、世代を超えた交流が盛んなことも、この温かい環境を支えている要因の1つではないでしょうか。
また、1人の教員が約15名の学生を担当するアドバイザー制度も本学ならではの魅力です。この制度により、学生一人ひとりに寄り添った指導が可能となり、相談しやすい環境が整っています。こうした手厚いサポート体制が、本学のアットホームな雰囲気をより強くしているのではないかと感じています。
先生ご自身について

-
Q.先生のご専門について教えてください。
私は、医薬品情報を基盤としたヘルスコミュニケーションについて日々研究を進めています。医薬品に関する情報は多くの人にとって難しく、適切に伝わらなければ誤解や不適切な使用に繋がる可能性があります。そのため、医療従事者や公的機関が患者さんにどのように情報を伝えるべきか、また、患者さんだけでなく一般の方がどのように情報を取得し、理解し、行動に移すのかを検討しています。
これに加えて、薬学教育に関する研究にも取り組んでいます。近年、薬剤師業務を取り巻く環境は大きく変化しており、大学も時代の変化に合わせた教育を提供することが求められています。そこで講義や実習の内容を新たに構築し、その教育効果を検証することで、より社会のニーズに応えられる薬剤師を育成できるよう努めています。
学生から見ると、教員や薬剤師などの大人と接すること自体どうしても構えてしまいがちですが、私は学生が気軽に話しかけられる雰囲気を大切にしています。もちろん適度な距離感は必要ですが、「ちょっと話してみようかな」と思ってもらえるような存在でありたいと意識しています。
また、学生の話をしっかり聞き、共有?共感することも大切にしています。アドバイジーとの面談や研究の場でも、学生自身の考えや思いを丁寧に聞き、適切に対応することで、より良い関係が築けるのではないかと考えています。
-
Q.研究の息抜きにしていることや趣味はありますか?
スポーツ観戦が趣味で、野球やサッカー、モータースポーツなど、国内外?種目問わず幅広く楽しんでいます。幼い頃から体を動かすのが好きで、長年サッカーをやってきました。今でも運動は嫌いではありませんが、最近は息子と娘、2人の子どものスタミナについていけず、衰えを実感する日々です。プレーする側から応援する側へとシフトしつつありますが、それでもスポーツの魅力を存分に味わっています。
また、スポーツと医薬の関わりについても関心を持ち、スポーツファーマシストの資格も取得しました。選手の健康管理やドーピングの問題など、観るだけでなく支える側の視点でもスポーツに関わることができるのはとても面白いと感じています。


薬学について
-
Q.薬学の面白さを、
どんなところに感じていますか?薬学は、薬に関わるとても幅広い学問です。薬を創ることから患者さんに安全に薬を使用してもらうことまですべて薬学です。そのため、講義でも物理や化学、生物、衛生、薬剤、薬物動態、薬理、病態、法規、倫理、実務など学ぶことがたくさんあります。これらの分野は一見別々の分野に見えるかもしれません。しかしそれぞれを深く学ぶと繋がってくるのです。薬に関するジェネラリストでありスペシャリストになる、それが薬学の面白さだと思います。
薬学の最も良いところは、「総合力」に尽きるのではないでしょうか。たとえば薬剤師は、身体の仕組みから創薬まで多くの分野の知識を身に付けた上で患者さんと接しますが、非常に奥深い職業だなと感じています。私は全学年の学生に教えていますが、常に「臨床にどう繋がるのか」を絡めながら話すことを心がけています。
-
Q.昭和薬科大学の魅力は?
穏やかで優しい学生が多く、落ち着いた雰囲気が魅力の1つです。学生と教員の距離も非常に近く、一緒にBBQをしたり旅行に行ったり、そういったことが比較的多く行われている印象を受けます。また、昭和薬科大学地域連携センターも年々拡充しており、地域社会との近い距離感にも魅力を感じています。本学の学生が団地に居住し、団地の自治会が行う活動に協力していますが、学生たちがクリスマスのイルミネーションの飾りつけなどをして、地域の方々に喜ばれている姿を見ると嬉しい気持ちになりますね。
他にも、アドバイザー制度を中心としたきめ細やかな教育や薬剤師を多く輩出している点、国試のストレート合格率や研究能力など、レベルの高い教育環境も魅力の1つだと感じます。
先生ご自身について

-
Q.先生がご専門にされている社会薬学のこと、
また研究の面白さについて教えてください。社会薬学の分野では、社会に繋がる薬学についてさまざまな研究が行われています。非常に幅広い分野ですが、私は中でも疫学?薬剤疫学を専門にしてきました。薬学部の研究というと実験を思い浮かべる方が多いと思いますが、私は実験ではなくデータを用いた研究を行っています。研究をすること自体は楽しかったのですが、その中で研究をする使命のようなものを感じたことがありました。
疫学では、人のデータを用いて人間集団における健康状態とそれに関連する要因を明らかにします。動物を用いた実験では条件を均一にできますが、人は個体差が大きく、特に観察研究では各個人の特性が結果に影響を及ぼしてしまうこともあります。そのような特性が結果を歪めることをできる限り避けるように、研究をデザインしていくことが難しくまた面白いところです。そのため、疫学研究では研究計画書の作成にとても時間をかけます。
疫学研究の結果は人におけるエビデンスですので、診療ガイドラインなどにも活かされ、より直接社会に貢献できることにもやりがいを感じています。
私は学部生時代から、地域住民を対象としたコホート研究に携わってきました。主に高血圧や循環器疾患をテーマに研究を行ってきましたが、コホート研究では地域の方々から健康に関するデータをいただくため、調査で何日もその土地に滞在することもあります。地域の保健師の方々と行動を共にする中で、保健師さんが「住民のために調査を行う」と奮闘し、住民の方々も保健師さんを信頼している光景を見て、「自分もこの方たちの役に立てる研究を行いたい」と強く思ったことを覚えています。最近は、データを二次利用したビッグデータを扱うこともありますが、データの先には一人ひとりの人がいることを意識し、データを使うことへの感謝を常に持ち続けて研究を行いたいと思っています。
-
Q.研究の息抜きにしていることや趣味はありますか?
愛犬との時間で癒されています。犬を通して近所の方々と知り合えたり、町田市周辺には自然豊かな魅力的な場所がたくさんあることを知ることができました。


薬学について
-
Q.昭和薬科大学の魅力は?
薬剤師国家試験をクリアするためには激烈な努力が必要なのに、決して殺気立つことのない平穏な校風。学内にはいつも優しい笑い声が漂っています。こんな環境で6年間を過ごせば、一生の友ができるに違いありません。また、自分がやりたい研究を、教員をはじめとした周囲が支えてくれ、自発的に学ばせてくれる懐の深さもあります。もちろん国家試験の合格率も悪くないですし(まだまだ上を目指しますが)、社会で活躍する卒業生がたくさんいるのは伝統校ならではの強みです。
-
Q.昭和薬科大学には、
どんな学生が多いんでしょう?昭薬生はスリー「O(おおらか?おおざっぱ?おとなしい)」とよく言われます。競争心が足りないとか、元気が足りないと勘違いされることもありますが、私は違うと思います。競争心は心の中で燃やすものだし、声の大きさだけが元気のバロメーターではありません。みんな自分から笑顔で挨拶してくれるし、実は負けず嫌いだし、いざというときには行動力もあります。ただ、「自分が!」という我を出さないだけです。
実務実習先の薬剤師の先生方からは、穏やかな昭薬生のキャラクターを褒めていただくことが多いです。薬剤師は、病に苦しむ患者さんに寄り添う職業。知識や能力も大切ですが、一緒にいて安心できる人柄こそ重要です。昭和薬科大学のアットホームな雰囲気が、そんな医療人を育んでいるのだと思います。
先生ご自身について

-
Q.小泉先生は昭和薬科大学OBなんですね。
2000年に学部卒、2005年に博士課程を修了し、外部で1年間研究をしてから、2006年に教員として昭和薬科大学に戻ってきました。助手として迎え入れていただく際、教授からは「研究の推進力になってくれ」という言葉をいただきました。学生の見本となるような研究姿勢を示しながら、学生と教授を結ぶパイプ役でありたいと考えています。
-
Q.趣味や、研究の息抜きに
していることはありますか?研究が大好きなので息抜きは必要ありません。むしろ、もっと研究したいのに1日が24時間しかないことにストレスを感じているくらいです(笑)。
また、教育も非常に奥深いです。教員が学生に接することができる時間は、たった6年程度。この間に多くのことを学んでもらい、成長してもらうにはどうするべきかを考え、いつも頭を悩ませています。すると学生に「先生、そんなしかめっ面してると話しかけにくいです」と言われます。質問しやすい雰囲気さえ作っておけば、学生は自ら学んで成長してくれると気づかされました。教員が学生に教えるという一方通行ではなく、教員が学生から学ぶことも多くあるのです。私自身、まだまだ成長途中と感じます。教員なのに意外でしょ?


薬学について
-
Q.薬学部で学ぶ心理学とは
どのようなものですか?私が担当する講義は1年次の「人と文化」という教養科目シリーズの中の「人の行動と心理」という科目です。内容は医療にかかわる心理学に限定せずに、臨床、発達、コミュニティ、環境など心理学の概論的な部分から始めて、自己理解や他者理解、人の心に影響を及ぼす社会的な要因などにも触れています。また、終盤には、将来薬剤師として患者さんと接するときに必要となるファーマシューティカル?コミュニケーションのスキルなども紹介しています。
-
Q.心理学は具体的にどのように役立つのでしょう?
2015年に改定された文部科学省の薬学教育モデル?コアカリキュラムでは、薬剤師の対人業務としての側面が強調されています。患者さんのために医療人として貢献するのに必要な「疾病が心理に及ぼす影響」や「服薬の心理」などの知識が重視されています。さらに、医師や看護師らとのチーム医療では、他者の意見を尊重しながら自身の専門性を発揮するためにコミュニケーションスキルも必要で、在学中には実習や社会に出たときに応用できるように基本的な知識やスキルまでは習得することが求められています。心理学はすぐに結果が出る学問ではありません。いつか役立つかもしれないと思いながら主体的に学ぶことが大切です。たとえば病院に勤める薬剤師なら、時に生死に関わるシリアスな状況に直面することもあります。そんな時に、患者さんやご家族に寄り添って安心を与えられる態度やことばが自然に出てくるために必要な分野だと言えるでしょう。また一方で、自分のスタイルを理解することで、厳しい医療現場で働く際のストレス対処もできるようになるかもしれません。
他者に共感しながら、自分らしい仕事や暮らしをしていくために大切な考え方やコツについて学ぶこと。それが、薬学生が学ぶ心理学のテーマかもしれません。
-
Q.昭和薬科大学は、
なぜ「教員と学生の仲が良い」のでしょう?バーベキューやお花見など、教員と学生が一緒に盛り上がっているのをよく見かけます。アドバイザー制度や研究室など少人数で一緒に活動することが多いので、仲良くなりやすいのでしょうね。私たちの研究室でも今度カレーパーティを開く予定です。
私は臨床心理士として「ここほっとルーム」で学生相談にものっています。悩みがある学生が気軽に来られるようにオープンに迎え、親身に話を聞くことを心がけています。
先生ご自身について
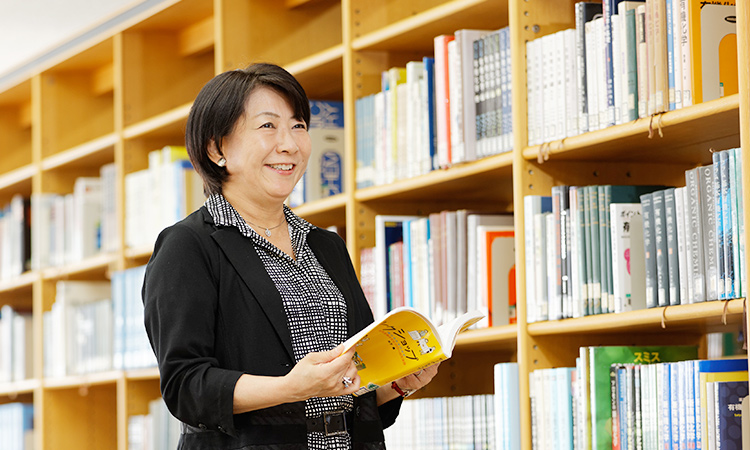
-
Q.趣味や、研究の息抜きにしていることはありますか?
ウォーキング、目指せ毎日1万歩。くいしんぼうなので、料理やおいしいものを食べに行くのが好きです。また、時間ができたら旅をしたり映画を観たり、ヨガもちゃんと習ってみたいです。環境を変えたり運動をしたりすることは、心をスッキリさせるためにも大切だと思います。


薬学について
-
Q.薬学の面白さを、
どんなところに感じていますか?病気の治療や診断には、その発症や進行のメカニズムを明らかにすることが重要です。体の中でどんなことが起こっているのか(特に脳の仕組み)を知りたいと思い、この分野に携わるようになりました。複雑な生命現象に向き合うのは面白く、知的探究心が刺激されます。今は生体イメージング(画像診断)の技術を使って、病気の原因となる分子の動きを明らかにする研究開発をしています。
-
Q.昭和薬科大学の魅力は?
大学教員というよりは高校の先生のように、熱い志をもって親身に指導する教員が多いです。学生同士も先輩?後輩の垣根を越えて仲が良く、アットホームな校風です。特に私は総合大学出身なので、国家試験合格に向けて教員と学生が一丸となって取り組む熱気を、とても新鮮にまぶしく感じています。
先生ご自身について
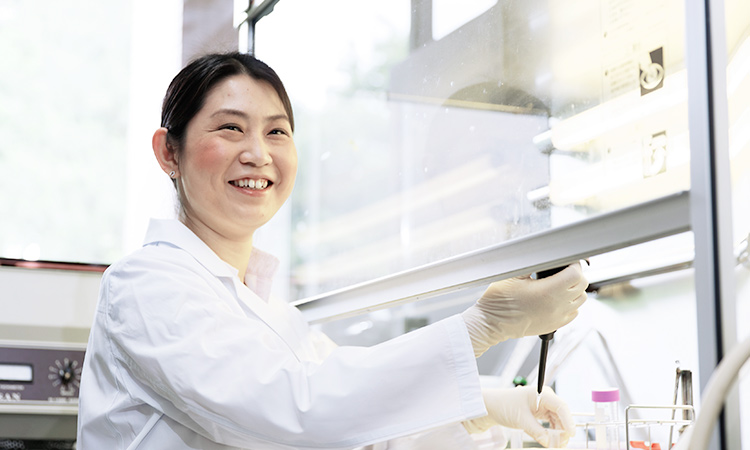
-
Q.学生に接する時に
意識していることはありますか?私は研究指導で学生に接することが多いのですが、学生には研究活動を通して自発的な動きを身につけられるようになってほしいと思っています。特に問題に直面した時には、まず自分で調べて、自分で考え、自分で解決する行動力が必要となります。これは研究に限らず、将来、どのような進路に進むとしても必要な力ですよね。ですから、やる気を引き出すような働きかけをしようと日々努めています。学生が萎縮すると困るので、大阪出身ですが関西弁で説教するのは封印しています(笑)。
-
Q.研究の息抜きにしていることや、
趣味はありますか?意外と言われますが、アウトドアが好きです。休日には山や海に出かけることが多く、時々バーベキューなどを楽しんでリフレッシュしています。


薬学について
-
Q.薬学の面白さを、
どんなところに感じていますか?生命はさまざまな生命現象、たとえば「糖を分解してエネルギーを作る」、「タンパク質を作る」、「不要なタンパク質を分解する」などのプロセスが複雑に絡み合って、調和されることで成り立っています。生命現象の根源的な理解は、化学の視点無しでは不可能です。私は薬などの化学物質を用いて生命現象をコントロールするという点に興味があり、薬学、特に有機化学の分野に足を踏み入れました。
薬の開発研究では分子に炭素をひとつ加えただけで、分子の形(構造)がまるで違うものに変わってしまったためにまったく効かなくなることがあります。つまり分子の形(構造)は、分子の機能(薬の作用)をコントロールすることができるのです。分子の新しい「形」を生み出すことで、創薬につなげていく研究をしています。
-
Q.昭和薬科大学の魅力は?
クラブ活動が活発で、薬科大学にしてはかなりの割合で学生がクラブに参加し、気の合う同士でエネルギーを発散しています。OB?OGとの交流も深く、たまに研究室にも顔を見せに来てくれます。病院や薬局で活躍する卒業生が多いので、さまざまな医療機関とのつながりがあるのも、伝統校ならではの強みですね。え、棚の上のバットとグローブは何?ですか? 年に一回、隣の研究室との親睦を深めるためにソフトボールの対抗試合をしているんです(笑)。レクリエーションやバーベキューなどで、教員と学生が一緒にワイワイしている様子をよく見られるのも、本学の特長だと思います。
先生ご自身について

-
Q.学生と接する時に
意識していることはありますか?講義は「どうして?」とか「なぜ?」と考えてもらえるように、意識して組み立てています。その上で有機化学が面白いと思ってもらえるように、研究の一端を紹介して好奇心を刺激します。研究を指導するうえでは、科学の考え方の流れをひと通り身につけられるように配慮しています。また、ディスカッションで学生のポテンシャルを引き出し、それぞれが目的?目標をもって学び、達成感を持てる機会を多く作るように努めています。
-
Q.研究の息抜きにしていることや、
趣味はありますか?家では2人の息子(2歳と0歳)の相手で手いっぱいです。やんちゃですが癒され、こちらが学ぶことも多い毎日です。